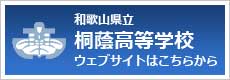トップ > 学校案内 > 校長室の窓から
校長室の窓から
質の高い授業を提供するために
変化の時代に最も必要な資質は、生涯にわたり「学び続ける力」を身に付けることだと考えています。そして、本校の教育目標として大事にしている言葉「桐蔭は、自ら人生を切り拓く人を育てます」、これを可能にする重要な資質もまた学び続けることであります。けれども、これが求められるのは、生徒だけではありません。変化の時代を生き抜いていく生徒たちに必要な力を身に付けさせるために、私たち桐蔭教職員も学び続けていく必要があると思っています。校庭に桐の花が咲いています
校庭に桐の花が咲き、最も桐蔭の校庭らしい姿を演出してくれています
ホームページを新しくしました
念願であった桐蔭HPを新しくしました。これまでのHPは、デザインも古く、また更新が難しかったため、学校の多様な情報を即座に、また楽しくお伝えすることができず申し訳なく思っていました。
新しくなったHPは、デザイン性にも優れ、更新も簡単にできますので、学校行事等はもちろんのこと、部活動等での生徒の活躍ちょっとした校内におけるエピソード、学校からのお知らせ、PTAの皆様方の活動等、さまざまな情報を即座にお伝えしていく予定です。
「改革と伝統」を胸に、生徒とともに学び、躍動感あふれる桐蔭の姿を是非ご覧になってください。
桐蔭におけるキャリア教育とは
本校では、全国で初めていわゆる進学校における「キャリア教育」を本格的に実施しています。なぜ、桐蔭でキャリア教育が必要なのか。桐蔭における「キャリア教育」の意義について考えます。
校長 岸田 正幸
「トビタテ!フォーチュンクッキー留学JAPAN」という曲をAKB48が歌い、全国の大学生と文部科学大臣をはじめとした文部科学省の役人がこぞって踊る姿がYouTubeで流れています。文部科学省が、全国の大学に依頼をしたら、本当にそんなことをするのかと各校から問い合わせがあったとのことで、その面白さが受けてか、アクセス数はすでに60万件になろうとしています。もちろん、文科省は本気で作っていて、AKB48を世に送り出した秋元康氏に作詞を依頼して、全国の若者たちに留学を呼びかけているわけです。それほど、若者たちが留学しなくなっている。その背景として、自分の将来が描きにくくなっている日本型雇用の現状の中で、あえて就職などで不利になるかも知れないといった未知数の指数を上げたくない意識が働いていることは容易に想像できます。一方で、これほど豊かで居心地のいい日本を離れる必要がないというのも大きな要因としてあるような気がします。風が吹けば桶屋がもうかる式の言い方をすれば、ウォシュレットトイレの普及が、若者の留学離れを後押ししているというようなことになるのでしょう。ますますグローバル化する社会にあって、豊かで暮らしやすい日本社会という現状の中で、こじんまりと生き続けようとする若者をどう鼓舞していくかという課題が浮かび上がってきます。
同時に、家族関係の変容や農村型むら社会の解体といった子どもたちの人間形成に大きな影響を与えてきた育ちの環境が変化する中、子どもから大人になる時期が遅くなる、或いは一人前になる力が減少しているということも課題です。こうしたことに対し、これまで教育の世界では、常套句的にその理由と思われることがらを指摘し、そこに責任を負わせることにより、終わらせてきたことが多かったように思います。曰く「地域の教育力が低下している」、「家庭の教育力が低下している」といった類のものです。そもそも、家庭の教育力ということについて言えば、私の経験からしても、昔の親は目の前の生活に精一杯で、放ったらかしで育てられた記憶しかなくて、その点、今の親は、若者たちの育ちが変化している中で、親であることの責任を社会から常に求められるという辛い立場にある。その社会的責任の問われ方が、「家庭の教育力が低下している」という言説になっているとも言えます。したがって、そうしたことに理由を求めるのではなくて、こうした子ども達の置かれた現状としっかりと向き合い、学校として何ができるかを考える。それが、「キャリア教育」であると、私は考えています。
言い換えれば、大学卒業後の彼ら彼女らの生き方にまで責任をもつ教育をしようという強い意志を示した教育、それが桐蔭におけるキャリア教育であるわけです。そのためには、当然「知力」も育てるべき大きなテーマになりますから、本格実施をする本年度春の入学生からは、「桐蔭の学び」と名付けた各教科の学び方を示した冊子を持たせ、学ぶことの意義という本質的なところまで掘り下げて学習を始めました。自らの将来との関連性、つまり、自分がどのような人生を歩むのかが見えにくい社会にあって、子どもたちの学びに対する意欲の低下、このことこそが最も大きな現代的教育課題であるととらえているからです。
学歴が将来の安定性を一定程度担保できた時代は、努力することの意味がわかりやすかったし、努力の結果として、多くはそれが職業人生に引き継がれていきました。もちろん、現在においてもそうした傾向は残存されてはいますが、かつてに比べれば、その相関は弱まり、反対に勉学的努力とは少し違うコミュニケーション能力や創造力、人間関係形成能力といったようなものが求められる時代となっています。もう少し言えば、勉学的努力の結果としての学歴だけで生きていける時代は既に終わり、社会において、継続的に成果を出すことによってしか評価されない、或いは学び続ける資質を有したものでないと評価されにくい時代になってきています。将来が見えにくいということと併せて、このことは、今の子どもたちに課せられた社会的な重荷であると言えます。加えて、冒頭の留学の話のように、豊かさの中でこじんまりと生きようとする子どもたちが増えてきたとすれば、グローバル化がますます進展する時代も踏まえ、これからの日本はどうなっていくのかと思うわけです。
桐蔭という学校の社会的責任というのは、こうした時代に求められる教育とは何かをしっかりと受け止めることであると思っています。「キャリア教育」は、こうした背景の中で、桐蔭でこそ真剣に取り組むべき教育課題であると考えているわけです。そこで、標題とした「桐蔭は、自ら人生を切り拓く人を育てます。」という言葉を本校におけるキャリア教育の目指すべきものとしました。
中学校と高等学校で毎週実施される「キャリア桐の葉」という授業を中心として、具体的な教育が始まります。走りながらではありますが、目指すべき生徒像をしっかりともって、その育成に向けた教育活動に取り組んでいるところです。
今、学校とは何か
これからの社会を生きる子どもたちの将来を考えたとき、これからの学校はどのような教育を追い求めていく必要があるのか。そして、桐蔭の教育に求められるものは何か。今、学校のあるべき姿を問い直します。
校長 岸田 正幸
将棋のプロ棋士とコンピュータソフトのどちらが強いか。電王戦と称する戦いが行われています。3回目の今春の戦いでは、5人のプロ棋士に5つのソフトが挑戦。なんと4勝1敗という結果で、プロ棋士側の完敗でした。
30年ほど前、ロボット開発の世界で「フレーム問題」が課題となりました。「フレーム問題」とは、コンピュータは、ある囲まれたフレーム(枠)の中にある情報を処理することは得意だけれども、フレームを外れた無限の情報をすべて分析し、置かれた状況に応じて適切な処理することはできないというものです。つまり、曖昧で複雑な情報を処理できないコンピュータの限界を指摘したものでした。
その点、将棋の世界は、局面局面により、無数の打つ手があるものの、1つのフレームの中にある情報を処理すれば済むという点で、コンピュータの得意分野であり、これからもプロ棋士がコンピュータに勝つことは難しいかもしれません。
今、コンピュータが自動で運転してくれる車が一部実用化しています。完全実用化に向けて各社が鎬(しのぎ)を削っていますが、こうした車の難しさは、人の飛び出しをキャッチして止まることはできても、同じ幅の道でも、周りに何もない草原の一本道なのか、近くに小学校がある道なのかの判断ができないし、走る時間帯によっても注意すべきものが微妙に変わる運転者の心遣いまで組み込むことが難しいところにあります。
けれども、「フレーム問題」から30年が経ち、コンピュータに巨大な脳を持たせて、それさえも乗り越えようと進化し続ける科学技術社会にあって、改めて「今、学校とは何か」ということを考える必要があると思っています。
学校とは、子どもたちが社会で生きていくために必要となる知識を教えるところに決まっています。事実、学校教育では、その知識を易しいものから難しいものへと系統的に並べ、それを効果的に教えることにより定着させることを中心とした教育を行ってきました。
もちろん、その役割は今後とも変わることはないでしょう。けれども、これまで述べてきた科学技術の進歩の中で、或いは様々な情報が簡単に手に入り、1つの情報が即座に世界を飛び回る高度情報化社会にあって、これまで人の能力を価値づける基本的な指標としてきた「記憶が力」であった時代は、明らかに終わりを告げようとしています。それよりも、何が正解なのかわからない、むしろわからないことが多い社会の中にあって、曖昧で複雑な情報を処理する「知」というものが、新たな指標となりつつあります。
「生きる力」や「人間力」の育成が求められたり、思考力や判断力を身につけさせる授業の必要性が説かれたり、コミュニケーション能力が社会では必要とされたりするのも、実は新たな「知」の指標への転換と同じ文脈の中で語られているわけです。
学校がしっかりと子どもたちに必要な知識を伝達し、それをすればある種の権威性が担保された時代は終わりました。学校での学びと将来との関連性が見えにくい子どもたち。受験終了後に剥落する可能性のある記憶の「知」の危険性。そうした本当の意味で学校が抱える課題をしっかりと認識し、桐蔭は、「今、学校とは何か」という問いに真摯に向き合っていきたいと思っています。
過去の校長室の窓から
校長室の窓で、これまでお伝えしてきたものです
TEL:073-436-7755 FAX:073-436-7766